夏目漱石『草枕』解説、連載第8回。 今回は、漱石が一般読者のために挙げた「雪舟・蕪村」という記号の奥底に潜む、真の南画論・文人画的美学を解剖します。
漱石が第六章で苦闘した「複雑な心持ち」の正体は、明時代の正統派画論である**董其昌(とうきしょう)の『画禅室随筆(がぜんしつずいひつ)』**に端を発する、東洋の体系的な美学観点なくしては語れません。また、レッシングの『ラオコーン』に代表される西欧的詩画分離論を、漱石がいかに東洋的な「詩画一体」の文脈で乗り越えようとしたのか、その知的な格闘を浮き彫りにします。
1. 董其昌『画禅室随筆』に見る画論の体系
漱石が「雪舟、蕪村は単純だ」と言い切る背景には、南宗画(文人画)の最高峰とされる**「気韻生動」**の極めて高度な要求があります。董其昌はその著書で、画を評価する基準を個人の技量ではなく、**学問・人格・旅(経験)**に求めました。
体系的観点のまとめ
董其昌および日本の画論(『丹青若木集』等)における評価軸は以下の三点に集約されます。
- 気韻(きいん): 作者の胸中にある高潔な気質。技法ではなく「人格」が滲み出るもの。
- 筆力(ひつりょく): 熟練した筆捌き。ただし、単なる技巧ではなく、内面のエネルギーが線に定着していること。
- 脱俗(だつぞく): 世俗的な「成功」や「富」を感じさせない、清らかな空気感。
【出典】董其昌『画禅室随筆』 原文: 「読万巻書、行万里路、胸中脱去塵濁、自然丘壑内営。立成鄄鄂、随手写出、皆為山水伝神。」 対訳: 万巻の書を読み、万里の道を旅せよ。そうすれば胸の中から塵のような俗っぽさが消え去り、自然と山水の風景が心の中に形作られる。心の内に基礎ができたなら、筆を動かすままに描き出せば、そのすべてが山水の真髄(神気)を伝えるものとなる。
漱石の主張との関係: 漱石が第六章で求めているのは、この「万巻の書」によって醸成された複雑な人格の投影です。単に風景を写生するのではなく、自身の複雑な精神(ムード)がキャンバスに定着することを求めており、それはまさに董其昌が説く「胸中の丘壑(きゅうがく:心の内の風景)」を外部へ吐き出す作業に他なりません。
2. 「冲融」と「澹蕩」――詩中の境地
主人公が「これだ」と膝を打つこの二つの言葉は、東洋詩学において「作為のない自然な融合」を指す最上の形容詞です。
「冲融(ちゅうゆう)」の出典
【出典】王維『贈呉官』 原文: 「悠然遠山暮、独向衡門中。冲融和気洽、恬澹道心同。」 対訳: 悠然と遠くの山に日が暮れ、独りわびしい門へと向かう。和やかな気がしっとりと溶け合い(冲融)、静かな道心が(自然と)一つになる。
「澹蕩(たんとう)」の出典
【出典】謝霊運『登江中孤嶼』 原文: 「雲日相輝映、空水共澄鮮。……澹蕩和風至、荏苒霽波還。」 対訳: 雲と太陽が互いに輝き映じ、空と水は共に澄み切っている。(……中略……)のどかな風がゆったりと吹き(澹蕩)、移ろいゆく晴れやかな波が帰ってくる。
解釈の確度: これらの詩に見られるのは、**「個の消失」**です。漱石が「鼻から呼吸もしたくない」と述べるのは、自己が自然の一部として、あるいは「冲融(溶け合った気)」の一部として存在する幸福を指しています。
3. 西欧の詩画分離論 vs 東洋の詩画一体論
漱石は、レッシングの『ラオコーン』を引用し、西欧的な芸術の「境界線」に挑戦します。
対比構造
- 西洋(レッシング『ラオコーン』):
- 絵画: 空間的・静止的(一瞬のポーズを描く)。
- 詩: 時間的・連続的(行為の継起を描く)。
- 主張: 詩が絵画の真似(視覚的描写の羅列)をすると、時間の流れが死んで退屈になる。
- 東洋(南画・文人画の伝統):
- 詩画一体: 「詩中に画あり、画中に詩あり(蘇軾)」。
- 主張: 詩も画も、作者の「気韻」を表現する手段に過ぎず、両者に本質的な境界はない。
漱石の統合的主張
漱石は、他の著作(『文学論』や随筆『草枕』執筆時の書簡)において、以下のような境地を理想としています。
「余が求むる所は、人事の葛藤を離れたる一点の静境なり。……詩も画も、唯(ただ)この静境を写し得ば足る。」
第六章における漱石の独創性は、「空間的なムード(画的要素)」を「時間の流れを伴わない詩(言語)」で定着させるという点にあります。彼はレッシングの「詩は時間的であるべきだ」という規範をあえて無視し、言語を「空間(ムード)を凍結させるための素材」として再定義したのです。
4. まとめ:壺中の天、青磁、そして冲融
- 壺中の天: 俗世の論理(時間や利害)から切断された、独自の美学空間。
- 青磁: その空間を象徴する、温潤で硬質な「器(うつわ)」。
- 冲融・澹蕩: その器の中に満たされた、主客未分の「空気(ムード)」。
漱石が雪舟や蕪村に満足しなかったのは、彼らが「一瞬の美」を捉えるには長けていても、現代(明治)の文人が抱える**「複雑で重層的な知性の飽和状態」**を表現するには、あまりに「形式的」すぎると感じたからです。彼は『画禅室随筆』が求めるような、全人格的な「気韻」の表出を、詩と画の境界が溶ける瞬間(第六章のラスト)に求めたのです。


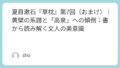

コメント