夏目漱石の『草枕』は、単なる紀行小説ではありません。それは、西洋から流入した「油絵的な写実」に対し、東洋の「文人画(南画)」の精神がいかに優位であるかを宣言した、知的なマニフェストでもあります。
漱石は冒頭で、芸術の本質を次のように表現しました。
「丹青(たんせい)は画架(がか)に向って塗抹(とまつ)せんでも五彩(ごさい)の絢爛(けんらん)は自おのずから心眼(しんがん)に映る。」
ここで使われている**「丹青」**とは、もともと赤(丹)と青の絵具を指しますが、中国の古典では「絵画」そのものを象徴する言葉です。
- 出典の背景:唐代の詩聖・杜甫が、画家の曹覇を讃えた詩『丹青引(たんせいのもり)』には、こうあります。
- 原文: 「丹青不知老将至、富貴於我如浮雲。」
- 対訳: (絵画(丹青)に没頭して老いが迫るのも知らず、富や名声などは私にとって浮雲のようなものだ。)
漱石はこの杜甫の精神を引き継ぎ、実際にキャンバス(画架)に向かって絵具を塗るという「行為」よりも、心の中に「丹青(芸術の本質)」を抱いていることの尊さを強調しています。
精神のカメラ「霊台方寸」と俗世の対比
漱石はさらに、私たちの心を「カメラ」に例えてこう述べます。
「ただおのが住む世を、かく観じ得て、霊台方寸(れいだいほうすん)のカメラに澆季溷濁(ぎょうきこんだく)の俗界を清くうららかに収め得うれば足たる。」
ここで登場する**「霊台」「方寸」**という言葉は、いずれも東洋哲学における「心」の別称です。
- 出典の背景:『荘子』庚桑楚(こうそうそ)篇
- 原文: 「霊台者、有持而不知其所持、而不可持者也。」
- 対訳: (心(霊台)というものは、それを支える主体がありながら、何によって支えられているかを知らず、また意識的に操ることもできないものである。)
現実の世界がどれほど**「澆季溷濁(道徳が衰え、乱れた状態)」**であっても、自分の心のレンズ(霊台方寸)を清らかに保っていれば、世界は美しく映し出される。外側の世界を変えるのではなく、自らの「観方」を変えることで苦界を芸術に変えるという、文人の徹底した主観主義がここに結実しています。
表現を超越した「無声の詩・無色の画」
漱石が説く「非人情」の境地は、形ある作品(アウトプット)すら超越していきます。
「この故に無声(むせい)の詩人には一句なく、無色(むしょく)の画家には尺せっけんなきも……あらゆる俗界の寵児よりも幸福である。」
この思想の背景には、北宋の文豪・蘇軾(蘇東坡)が唱えた有名な芸術論があります。
- 出典の背景:蘇軾『書摩詰藍田煙雨図』
- 原文: 「味摩詰之詩、詩中有画。観摩詰之画、画中有詩。」
- 対訳: (王摩詰(王維)の詩を味わえば、詩の中に画がある。王摩詰の画を観れば、画の中に詩がある。)
文人趣味において、詩と画は表現方法が異なるだけで、その根底にある「気韻」は同一です。漱石はここからさらに踏み込み、「一句の詩も、一尺の絹(画材)も持たずとも、世界を芸術的に捉える心さえあれば、その人は既に詩人であり画家である」と説きました。これは「胸中の丘壑(きゅうがく:心の中の自然)」を重んじる文人画の極意を、近代小説という枠組みで見事に再定義したものです。
自然の「悠然」とした絶対的な存在感
山道を登る主人公の前に立ちはだかる土手や岩。漱石はそれらを次のように描写します。
「掘崩ほりくずした土の上に**悠然(ゆうぜん)**と峙そばだって、吾らのために道を譲る景色けしきはない。」
この**「悠然」**という二文字には、漱石が最も愛した詩人・陶淵明への深い敬意が込められています。
- 出典の背景:陶淵明『飲酒』其の五
- 原文: 「采菊東籬下、悠然見南山。」
- 対訳: (東のまがきのふもとで菊を摘んでいると、ふとした拍子に(悠然と)、遥か南の山が目に飛び込んできた。)
陶淵明の説く「悠然」とは、単なるのんびりした様子ではなく、「作為がなく、自然と一体になった瞬間」を指します。漱石は、道を譲らない無愛想な自然を「悠然」と呼ぶことで、人間中心主義的な知の執着を皮肉りました。自然は人間の都合などお構いなしに、ただそこに超然として存在する。この自然の「動じなさ」を肯定的に受け入れる態度こそ、漱石が求めた「非人情」の象徴なのです。
まとめ:漱石が提示した東洋的救済
本記事で見てきた通り、漱石のレトリックはすべて中国古典の深い教養に裏打ちされています。
| 漱石の用語 | 出典となる古典 | 共通する精神性 |
| 霊台方寸 | 『荘子』 | 執着を捨て、鏡のように世界を映す「虚」の心 |
| 無声・無色 | 蘇軾(王維論) | 形よりも、その奥にある「気韻」を重んじる |
| 丹青・五彩 | 杜甫・五行説 | 世俗の価値観を超えた、真実の色彩 |
| 悠然 | 陶淵明 | 人間社会の理屈から離れ、自然に没入する境地 |
智・情・意という近代西洋的な「個」の苦しみに直面していた漱石にとって、これらの漢文学的教養は単なる知識ではなく、エゴを捨てて世界と和解するための、切実な**「精神の安全装置」**でした。
山路を登る一歩一歩は、そのまま「苦しい近代日本」から「自由な東洋的芸術世界」への移動であったのです。
次回の連載では、この「非人情」の思想が、漱石の晩年の理想である「則天去私」へとどのように繋がっていくのか、そのミッシングリンクを明らかにしていきます。



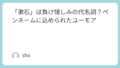
コメント