宿の欄間に掲げられた「竹影払階塵不動」。この七字を見ただけで、主人公(余)はそれが江戸時代に中国から渡来した禅僧・高泉和尚の筆致であると見抜きます。この鋭すぎる鑑識眼の裏には、黄檗宗の歴代の僧侶たちに対する、漱石ならではの緻密な分析がありました。
1. 黄檗三筆の「面白味」と高泉の「至高」
主人公は、黄檗宗の基礎を築いた「黄檗三筆」たちをそれぞれこう評価しています。
| 僧侶名 | 書風の特徴(文人的な感想) | 漱石の捉え方 |
| 隠元(いんげん) | 雄大で包容力があり、明代のエネルギーを直接伝える。 | 「面白味」はあるが、どこか開祖ゆえの重厚さが勝る。 |
| 木庵(もくあん) | 骨格が正しく、端正。三筆の中で最も整った美しさ。 | 端正すぎて、文人が求める「枯れた味わい」には一歩譲る。 |
| 即非(そくひ) | 奔放で勢いがあり、禅的な瞬発力に満ちた豪放な筆致。 | 勢いが勝り、やや「雅」の静寂には遠い。 |
これら三筆の巨星たちを差し置いて、主人公は第5代の**高泉(こうせん)**を「一番」だと断じます。
「高泉(こうせん)の字が一番蒼勁(そうけい)でしかも雅馴(がじゅん)である。」
ここでいう**「蒼勁(枯れて力強い)」かつ「雅馴(正統で雅やか)」という評価は、単なる好みの問題ではありません。 初期の三筆が持っていた「異国情緒や圧倒的なエネルギー」が、高泉の代に至って、日本の文人社会に美しく溶け込み、「高度な洗練と精神的な静寂」**へと昇華された。その「一歩引いたところにある強さ」にこそ、漱石は真の教養(文人趣味)を見出したのです。
2. 「大徹」という人物を推理して楽しむ
ここで面白いのは、主人公がこの書を「真筆(本物)か偽物か」という鑑定の場として見ていないことです。彼は「落款(サイン)は大徹だが、筆致はどう見ても高泉だ」と気づいた瞬間、そこにある**「知的な遊び」**を楽しみ始めます。
なぜ「高泉」を写したのか?
主人公は、この額が「昨今の新しい紙」に書かれたものであることを見逃しません。つまり、この宿の主人が、自ら筆を執って高泉の書風を完璧に模写し、そこに自分の号である「大徹」と記したのだと推測します。
ここに文人趣味の極致があります。
- 高泉を選ぶセンス:誰でも知っている三筆ではなく、あえて高泉の「蒼勁雅閣」を選ぶという主人の鑑識眼。
- 写(うつ)すという行為:単なる真似ではなく、高泉の精神性を自分の肉体(筆運び)で再現しようとする修練。
- 大徹という署名:高泉を完全に憑依させた上で、最後に自分の名(大徹)を置く。これは、過去の偉大な魂と対話し、自分の精神をそこに重ね合わせる「文人的な呼吸」です。
3. まとめ:書を通じて「同類」を見つける
「ことによると黄檗に大徹という坊主がいたかも知れぬ。……どうしても昨今のものとしか受け取れない。」
主人公は、この額を通じて、まだ見ぬ宿の主人の正体を確信します。
「この宿の主人は、自分と同じように高泉を愛し、その筆致を再現できるほどの教養と腕前を持った、筋金入りの文人に違いない」と。
この欄間の七字は、単なる飾りではありません。主人公と主人が、言葉を交わす前に「書」という教養のコードを通じて握手を交わした、**「非人情なコミュニケーション」**の始まりなのです。

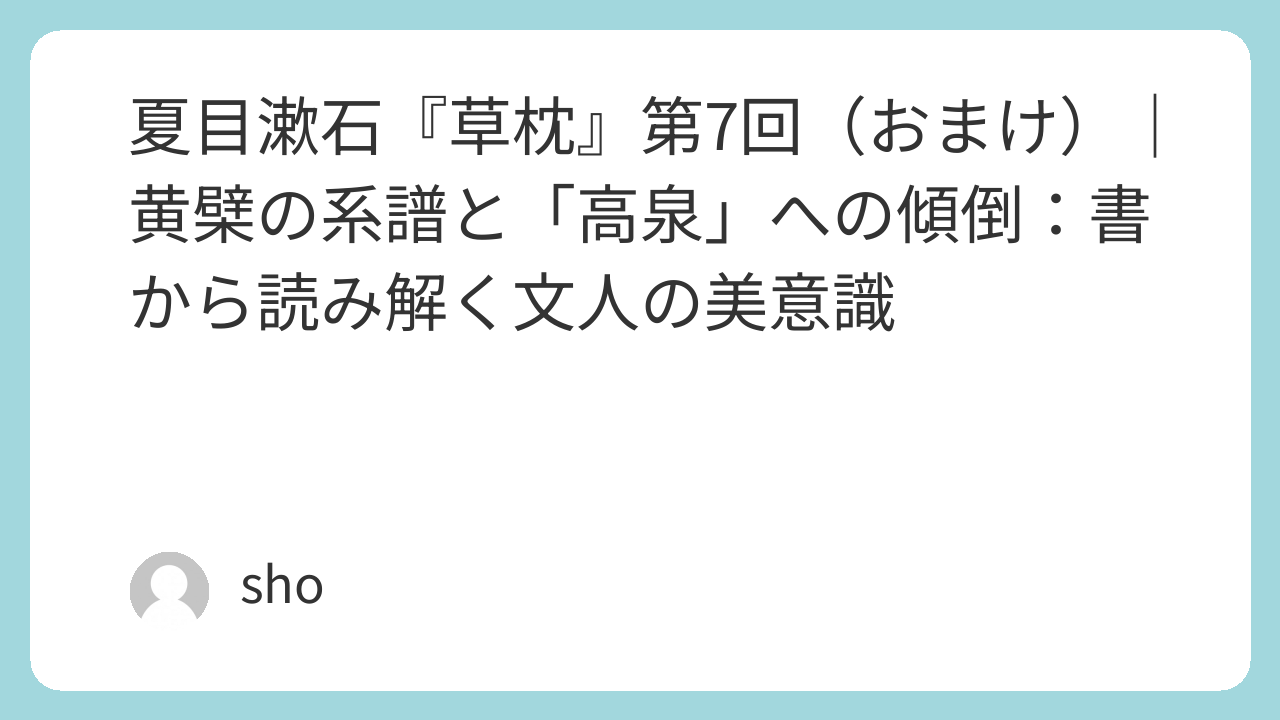


コメント