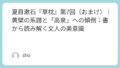さて、今回から第三章へと入ります。これまで道中の自然や茶店での対話を通じて「非人情」を模索してきた主人公(余)は、ついに目的地である「那古井の宿」に腰を据えます。
ここでの体験は、どこか現実味を欠いた「カンヴァスの中」のような不思議な手触りを持っています。まずは、日本的な怪異と情緒が混ざり合う、宿の最初の夜を見ていきましょう。
1. 欄間に掲げられた「非人情」のスタンス
宿に落ち着いた主人公の目に飛び込んできたのは、黄檗宗(おうばくしゅう)の僧侶によるものと思われる額の文字でした。
「文字(もじ)は寝ながらも竹影(ちくえい)払階(かい)をはらって塵不動(ちりうごかず)と明らかに読まれる。大徹(だいてつ)という落款(らっかん)もたしかに見える。」
- 出典:『伝灯録』あるいは禅語
- 元の詩句は「竹影掃階塵不動、月輪穿海水無痕(竹の影が階段を掃いても塵は動かず、月の輪が海水を突き抜けても水に跡は残らない)」というものです。
- 解釈:
- これは、外界がどれほど動いても内面は泰然自若としている、まさに「非人情」の境地を象徴する言葉です。漱石はこの七字を見て、黄檗の高泉和尚のような蒼勁(そうけい)な筆致に感銘を受けます。この宿そのものが、日常の塵を動かさない「聖域」であることを示唆しています。
2. 若冲の鶴と「雅俗混淆」の夢
床の間には、江戸時代の天才絵師・伊藤若冲(いとう じゃくちゅう)の図がかかっていました。
「床(とこ)にかかっている若冲(じゃくちゅう)の鶴の図が目につく。……一本足ですらりと立った上に、卵形(たまごなり)の胴がふわっと乗(の)っかっている様子は、はなはだ吾意(わがい)を得て、飄逸(ひょういつ)の趣(おもむき)は、長い嘴(はし)のさきまで籠(こも)っている。」
- 背景:伊藤若冲の「一筆書きの鶴」
- 若冲といえば精密な彩色画が有名ですが、ここではあえて「世間に気兼ねなしの一筆書き」の飄逸(ひょういつ)さが強調されています。
この「画」のような空間で眠りについた主人公が見たのは、**「雅俗混淆(がぞくこんこう)」**の奇妙な夢でした。万葉の「長良の乙女」が、急に西洋の「オフェリヤ」に変わり、救おうとする自分はなぜか東京の「向島」を追いかけている。 漱石は、悟りを開いた禅師(大慧禅師)ですら夢の中の俗念には困ったという逸話を引用し、芸術家としての自分の未熟さを自嘲しています。
3. 月下の幻影と、消えゆく歌声
夢か現(うつつ)か分かぬまま、主人公の耳に届いたのは、あの「長良の乙女」の悲しい歌声でした。
「あきづけば、をばなが上に、おく露の、けぬべくもわは、おもほゆるかも……。今やむか、やむかとのみ心を乱すこの歌の奥には、天下の春の恨(うらみ)をことごとく萃(あつ)めたる調べがある。」
- 解釈:
- 音が消える瞬間の「憐れ」の深さ。主人公はその声を追い、障子を開けます。そこには月の光を浴びて、海棠(かいどう)の幹を背に立つ朦朧たる影法師——那古井の嬢様(那美)の姿がありました。
- 前章で老婆から聞いた「悲劇のヒロイン」の物語が、いま目の前で「月下の幻影」として立ち現れたのです。しかし、彼女が近づくにつれ、主人公は「世間話の垢(あか)」を恐れた自分を思い出し、再び「非人情」の布団の中へと逃げ込みます。
まとめ:日本的情緒から、漢文的深淵へ
今回の場面は、若冲の絵や黄檗の書、万葉の歌といった「日本的・禅的」なモチーフが主役でした。しかし、この「時計の音すら気にかかる」不眠の夜を経て、物語はさらなる知的な深化を見せます。
次回は、いよいよ漱石の真骨頂。宿の主人との対話や、より深遠な**「漢文学的な芸術論」**が展開される場面へと進みます。「非人情」という理想が、那美さんという具体的な「謎」を前に、どのように理論武装を強化していくのか。ご期待ください。